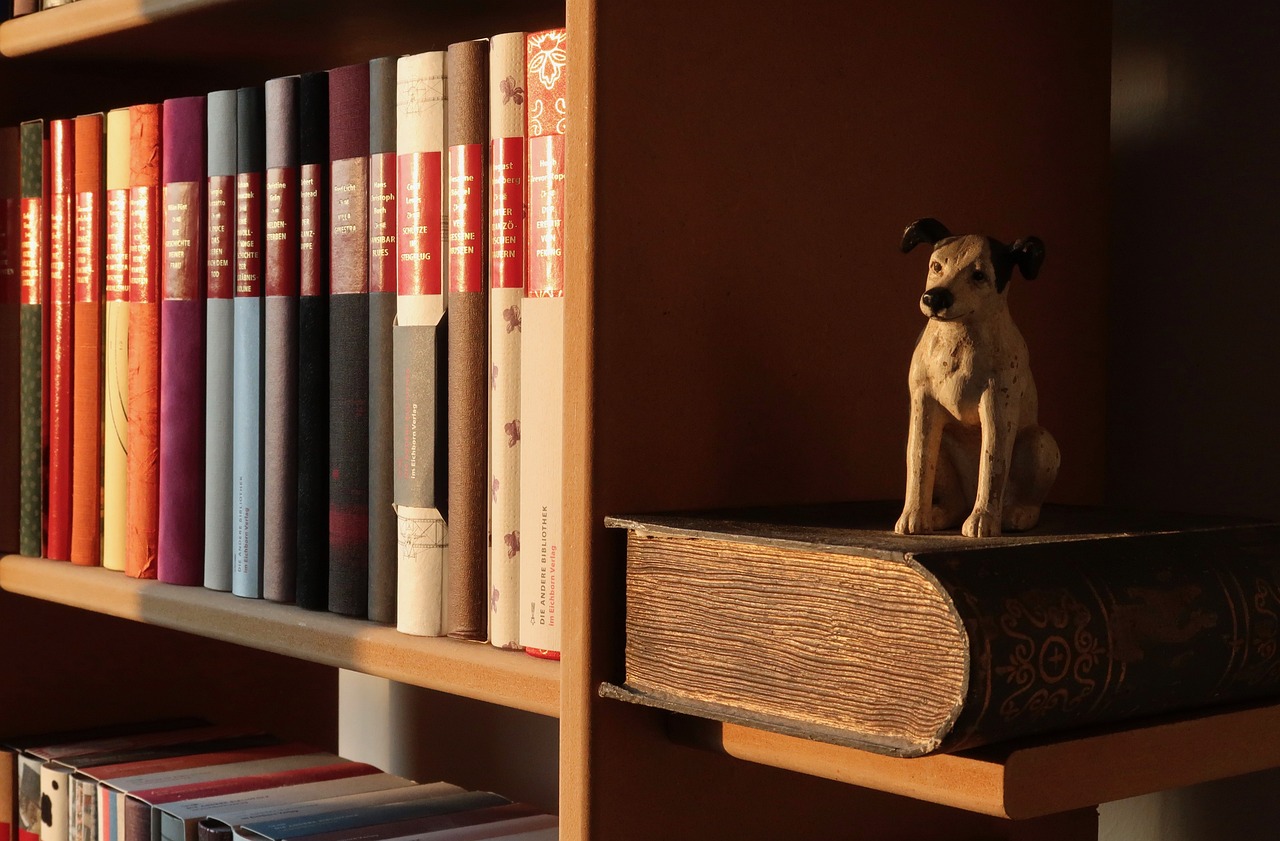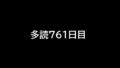前回の記事から時間が空いてしまいましたが、
ファストスロー(下)のライフハックをピックアップする続きです。
本はこちら👇
違う勘定で扱ってしまって損してしまう(メンタル・アカウンティング)
ボーナスが入った時、ご褒美に普段は買わないものを買ったりしませんか?
普段のお給料とは別の勘定として分けてしまう傾向のことをメンタルアカウンティングと言います。
ボーナスで多くお金が入る場合に普段とは違う使い方をして、多めに支出してしまっています。
似たような例として旅行があります。
「旅行費用」として予算を別に設定し、その範囲内で贅沢をすることがよくあります。
これは旅行用の予算と普段の生活費を心理的に切り分けていることで起きています。
個人的には普段できない体験にはお金を使うことは良い事だと思うので、多めに払ってもいいですが、同時に余計なお土産を買ってしまいかねません。
財布の口が緩くなることは認識しておいた方がよいと思います。
他にはクーポンや割引を使ったときに、「これで得した」と感じて、つい予定外の買い物をしてしまうことがあります。
金額で見ると無駄な支出ですが、心理的には割引の恩恵を受けたと思い込み、非合理的な行動につながります。
お酒でも注意が必要です。
食事代として決められた予算を使い切った後に、追加でお酒を頼んだ場合、お酒代を「楽しみのための予算」として心理的に別枠で管理してしまうことがあります。
最終的に全体的な支出が増えてしまいます。
頭の中で勘定を分けて管理することで、無駄遣いや過剰な浪費が発生する場合もあるため、自分がどのようにお金を分けて考えているか意識することが大切ですね。
状況によって好みや選択が変わる(選好逆転現象)
選好逆転現象(preference reversal)は意思決定の場面で人々が選択肢に対して一貫した評価をしない現象です。
ある選択肢を優先するはずなのに、実際の選択ではその選択肢を選ばない、という逆転した選好が現れます。
この現象は特に金銭的な意思決定やリスクに関する場面でよく見られます。
✅例
- 「90%の確率で100万円手に入るが、10%の確率で手に入らない」という投資Aと「確実に90万円手に入る」という投資Bがあった場合、投資Aの方がリターンが大きいので選ばれるべきだが、リスクを取るのが怖いため投資Bを選んでしまう
- (逆のようなこともあって、)ギャンブルで、「100万円を確実に手に入れるチャンス」と「1億円を得る可能性が50%、0円の可能性が50%」の場合に、合理的には、確実に100万円を選ぶのが理にかなっているが、実際は「1億円を手に入れるかもしれない」という夢を追って、ギャンブルを選ぶ
- ある商品が定価10000円で、今なら50%オフの5000円の場合、「5000円の価値に相当する商品」である場合でも、割引を受けているという感覚が強いため、実際にはその商品を購入する必要がないにも関わらず、無駄にお金を使ってしまう
選好逆転現象が起きることで損してしまうことを避けるには、冷静な判断と合理的な選択を意識的に行うことですね。
そのためにも、自分に本当に必要なものなのかを一歩立ち止まって考えることです。
幸せは長く続いた方がいいのか(持続時間の無視、ピーク・エンドの法則)
人は誰しも幸せでいたいですよね。
この幸せがずっと続くといいと思うものですが、幸せは長く続くといいのでしょうか。
逆に不幸は長く続かない方が良いのでしょうか。
普通に考えれば幸せは長く続けばいいですし、不幸は短く終わってほしいものです。
ここで、「持続時間の無視(duration neglect)」という現象があります。
持続時間の無視(duration neglect)とは、物事の「持続時間」がその体験の評価に影響を与えにくい現象のことです。
例えば以下のようなことです。
- 医療処置の痛みとして15分間続いた処置と5分間の処置があったとしても、最も痛かった度合いが同じなら、どちらも「とても痛かった」として同様に記憶されることが多い
- 旅行中の最も楽しかった瞬間や、最後の感動的な体験はその旅行期間の長さとはさほど関係ない
- 映画の上映時間が2時間であれ3時間であれ、映画を見終わった後の感想では「持続時間」よりも、映画の最も面白かった場面や結末に基づいて評価を決めることが多い
また、「持続時間の無視」に関係してくる法則として「ピーク・エンドの法則」と言うものがあります。
人々が体験の満足度や不満足度を振り返るとき、その体験がどのくらいの時間続いたかをほとんど考慮せず、最も強く感じた瞬間(ピーク)や終わりの印象(エンド)に基づいて全体の評価を決めてしまう傾向のことです。
これにより、サービスや体験のデザインにおいて、最も記憶に残る瞬間や終わりの印象を工夫し、全体の評価を高めるという戦略が立てられます。
以上より、
- 選択肢A: 3泊4日の旅行だが、観光スポットが少なく全体的に平凡
- 選択肢B: 1泊2日の旅行だが、絶景や特別な体験が詰まっている
という2択なら、選択肢Bを選ぶ方がいいですし、
- 選択肢A: 全体的に楽しいが、最後の結末が残念な映画
- 選択肢B: 前半は退屈だが、後半のクライマックスが感動的な映画
という2択なら、選択肢Bを見た方が満足度の高い時間を過ごせる可能性は高くなります。
レストランだと、ボリュームが多い料理ではなく、一皿が少なくても「驚くほど美味しい」料理を選ぶ方が良いです。
友人と過ごす時間は、長時間だらだらと一緒に過ごすより、短時間でも楽しい瞬間を共有する方が良いです。
娯楽は無駄に長いエンターテインメントよりも、短くても感動的なものを選ぶのが良いです。