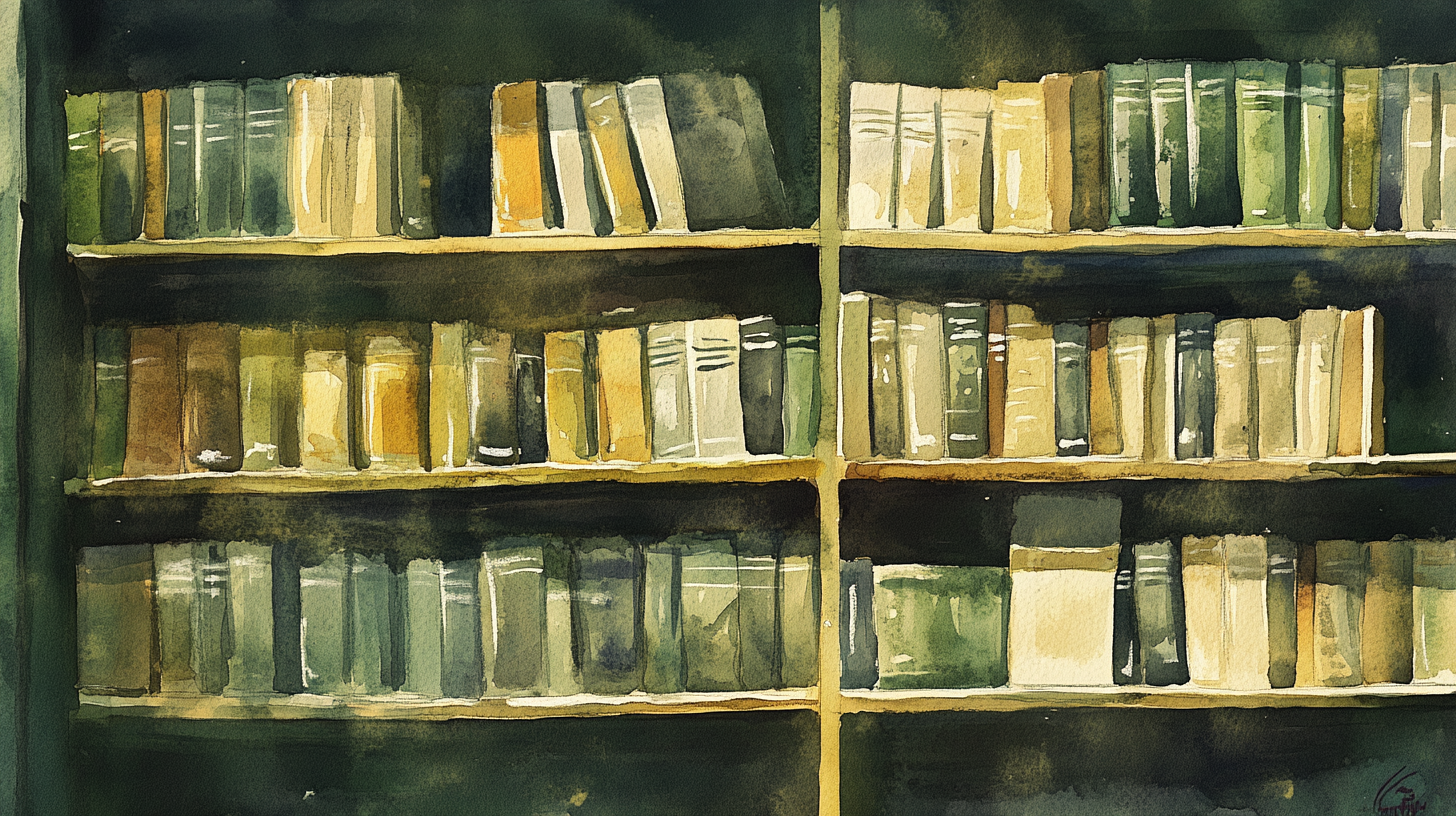はじめに
失敗から学ぶことは多いですが、できるだけ失敗はしたくないというのもあります。
さらには、その失敗の程度によっては取り返しのつかないことにもなるので、今回はそんな将来の失敗を予防するために「失敗の科学」という本を読んでみました。

「失敗の科学」
本書は失敗がどのように発生するのか、そしてその失敗とどのように向き合っていくべきかを実際に遭った事例と共に解説している。
また、実験を行った論文も元に人間が失敗を起こしやすくなる現象も説明しているので、失敗に対して非常に詳しく且つ専門性のある内容となっていた。
今回は本書から失敗について
- 失敗がどうして発生するのか
- 失敗に対してのマインドセット
をまとめてみます。
失敗の仕組み
失敗はどうして発生するのか。
その、失敗の仕組みを考える上で着目したいのが、医療業界です。
1999年、米国学研究所が発表したレポートによると、アメリカでは毎年4万4000~9万8000人の患者が回避可能な医療過誤によって死亡しているということを発表しています。(※参考1)
当然ながら、医療従事者が悪意があったり、やる気がないわけでもないです。
ではなぜこのような多くの医療ミスが起きるのでしょうか。
原因として挙げられるのは以下です。
- 複雑さ
- WHOでリストアップしている1万2420種類の疾患や障害は、それぞれ処置の手順がことなります
- 資金や人手不足
- 医者が常にとっさの判断を迫られていること
そして最後に挙げられる原因がもっと深いところにあり、それは医療業界以外にも当てはまります。
それは、組織文化そのもの関わる潜在的な要因にあります。
✅失敗の隠蔽
まず、人々は「自分自身」から失敗を隠します。
ミスに対して自尊心や職業意識が脅かされることで、失敗を公開することに苦痛を抱くことになります。
そして、失敗や欠陥に関わる情報が、放置されたり曲解されていき、進歩に繋がらない現象が起きます。
この失敗に対して向き合わない姿勢が学習の機会を奪い、次の失敗に繋がります。
✅上下関係
社会的な上下関係は部下の主張を妨げ、控えめな表現を使うことが多くなります。
結果的に大惨事に繋がります。
ここで問題は当事者の能力やモチベーションではなく、人間の心理を考慮しないシステムにあります。
隠蔽体質と強い上下関係のある環境では失敗が起き続けるわけですね。
大事なのは失敗から学ぶことです。
以下は本書の引用です。
何か失敗したときに、「この失敗を調査するために時間を費やす価値はあるだろうか?」と疑問を持つのは間違いだ。時間を費やさなかったせいで失うものは大きい。失敗を見過ごせば、学習も更新もできないだから。
「失敗の科学」
失敗を学ぶ際には調査が大事です。
目の前に見えていないデータも含めた全てのデータを考慮して、注意深く考え、物事の奥底にある真実を見抜いてやるという強い意志が不可欠になります。
さらに、失敗から学ぶために必要不可欠な要素として以下の2つも挙げられます。
- システム
- 失敗とは「起こってほしい理想」と「実際に起こってしまった現実」のギャップであり、このギャップを埋めるために、学習チャンスを最大限に活かすシステムが必要になってきます
- スタッフ
- システムが素晴らしくても、中で働いているスタッフからの情報が無ければ、なにも始められません
- ここで、スタッフが非難されることや自分の評判を落とすことを恐れて情報を提供しなければ、失敗につながります ⇒ スタッフのマインドセットがこのようなアンチパターンにならないようにしなければなりません
失敗へのマインドセット
上記では失敗の仕組みからあるべきシステムについて書きました。
ここでは失敗に対してのマインドセットについて書いていきます。
と、その前に、遺伝学者のアレック・ジェフリーズの大発見の話をします。
1984年、ジェフリーズはある大きな発見をします。
「DNA指紋」です。
これは、DNA鑑定の礎となった、犯罪学の革命です。
これにより、DNP鑑定は多くの事件を解決に導いてきました。
ジェフリーズが開発したDNA指紋を用いた鑑定手法は1980年代後半に実用化されましたが、2005年までに300人を超える受刑者の冤罪による無実が確定しています。
しかし、DNA鑑定で無実を獲得しても、警察や検事が自分たちのミスを認めないケースもあります。
つまり、不都合な真実を解釈で塗り替えることです。
正義の立場にある人がどうしてこのような過ちを犯すのでしょうか?
いや、正義の立場にある人だからこそ起きることなのでしょう。
人は自分の信念と相反する事実に対して、自分の過ちを認めるよりも事実の解釈を変えてしまう傾向があります。
次々に都合のいい言い訳をして事実を無視してしまうこともあります。
このような状況になった時の解決策として以下の2つのどちらかを選択します。
- 自分の信念が間違っていたことを認めること(ただし激ムズ。理由は自分が有能で無かったことを認めるのが怖いから)
- 否定
- これがアンチパターン。自分の都合のいい解釈で言い訳する。
1987年のモンタナ州の事件において、検察側が依頼して用意した捏造による証拠品がのちに明らかになります。
2000年にはDNA鑑定によって犯人が別にいることがわかるのです。
この検定結果に対するマイケル・マクグラスという検事の主張は耳を疑うレベルでした。
彼はこの事件で誤って捕まった人をキメラだと言ったのです。
キメラというのは2種類のDNAを持つ人間のことで、世界的にはわずかな例しか報告されていません。
キメラでないことも証明されてなお、マクグラスは間違えを認めませんでした。
ここで起きているのは
✅努力によって判断が鈍っている
ことです。
検察官は、たいてい自分たちが行っている事は単なる仕事ではなく使命だと思っています。
さらには、自分たちの能力に強い自負があります。
検察官になるには多くの努力が必要になります。
事件の捜査で検察も警察もその使命のもと、良い世の中にするためにと事件解決に励みます。
懸命に働き続けます。
そして、その努力の末に無実の人を刑務所に送り込んでしまう訳です。
「(無実の人を刑務所送りにすることは)プロが犯す失敗の中で最悪の部類に入る。外科医が間違って健康な方の腕を切断するようなものだ」
by 社会心理学者リチャード・オフシェ
頭脳明晰な学者ほど失敗によって失うものが大きいから保身のために自分の信念と事実とのギャップを埋めるように動いてしまいます。
自分の仮説に溺れないことが大事です。
自分がわかっていると思っていることの検証ばかりに時間をかけてしまわずに、まだわかっていないことを見出す作業を行うことの方が重要です。
失敗の学習チャンスを最大限に活かすプロセス
実際に、失敗に対して、学習チャンスを最大限に活かすにはどうすればいいのでしょうか。
それは失敗をとにかく繰り返すことです。(質より量!⇐これ大事!)
進化とは選択の繰り返しです。
進化や革新は、頭の中で完璧に組み立てられた計画によって生まれるものではなく、周りの世界に徐々に適応していき、変異していく事です。
だから、進化そのものに美しい計画はありません。
試行錯誤を繰り返してくことです。
選択を繰り返し、適応力の強い個体を残していく事。選択と淘汰の繰り返しによってたどり着きます。
直面する問題は単純ではありません。
だから、理論や図面上で答えは出せないので、実際に失敗を繰り返して学んでは解決していく事が大事です。
最後に
失敗を恐れず、失敗から学び、成長していきたいですね。