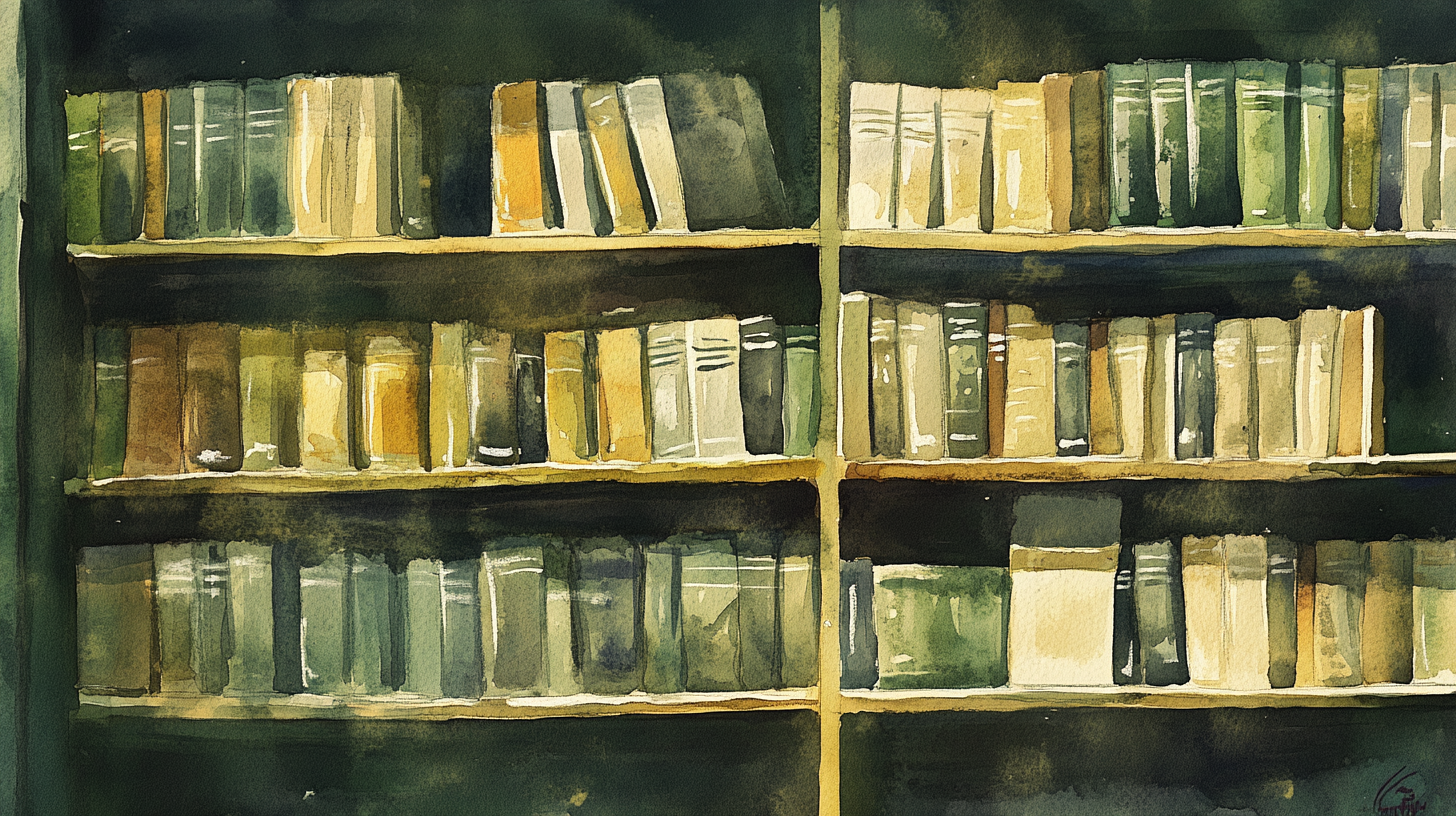はじめに
超有名な経済評論家の山崎さんの父から息子への手紙を読みました。
「経済評論家の父から息子への手紙 お金と人生と幸せについて」という本です。

「経済評論家の父から息子への手紙 お金と人生と幸せについて」
本書は父から子へ伝えたいことをリストから本にしたような内容になっています。
今回は僕がこの本から伝えられたことをまとめてみようと思います。
働き方
古い働き方と新しい働き方があります。
今は転職もしやすくなりました。
年功序列なんてなくなってきてもいます。
つまり新しい働き方できるような時代になっているのです。
古い働き方とは、
「安定した職を得て、出世して、労働を高く且つ長く売る」という働き方を指します。
いい就職先と言うのは所謂大企業であり、国家公務員になります。
ここで出世して、自分の労働時間単価を上げ、長く勤める。
あとは、医者とか弁護士とか、時間単価が高くてくいっぱぐれが無いような職業とかもいい職業と言われていたわけです。
この古い働き方では、大いに不自由な職業人生を送り、小さな確率で成功するものの、成功しても大金持ちにはなれません。
そして、つまらない。これはコスパが悪いです。
大企業に入っても、当面の職と収入の安定に満足し、ぼんやり過ごして人生のチャンスをどんどん失っていくわけです。
では、新しい働き方とはどうなものでしょうか。
新しい働きとは、効率性と自由を求めます。
必要なマインドセットは以下の2つ。
- ①常に適度な「リスクをとる事」
- ②他人と異なることを恐れずむしろそのために「工夫をすること」
「リスクを取らずに、他人と同じように働きたい」という動きは、不利な側への経済的な「重力」が働きます。
経済の世界では、リスクをとっていいと思う人が、リスクを取りたくない人から、利益を吸い上げるようにできているようです。
原題では、この差がよりはっきりと現れてきています。
学生は周囲と同じ「就活」を行って何十枚もエントリーシートを書き、仮に大企業に就職できたとしても、それは人生のゴールとは遠く、職業人生の魅力的なスタート地点ですらない可能性が大きいというわけです。
自分自身が「他人と取り替え可能な労働者」にならないような工夫が必要だということ。
労働者に限らず、工夫のない人は損をする。これは責任論以前の経済の現実だ。他人と同じであることを恐れよ。無難を疑え。
正社員としてそこそこの会社に入れたら、非正規労働者よりも給料が少しいいかもしれないし、クビにはなりにくいでしょう。
でも、その立場が安住すると、一生、会社の奴隷のような存在になる可能性が高くなります。
これを回避するためには、他人と違う能力を持つことです。
- それを仕事に使わせてもらうようにアピールしたり、
- 副業ができるようになったり、
- 転職のリスクをとるようになったり、
- 経済的な備えを持って会社と強く交渉できる立場を確保したり
「他人と同じ」を求めるだけでは幸せにはなれません。
今の状態に満足せず、適度なリスクを取りながら、他人と同じような世界に入り浸らないようにしたいですね。
自己投資
稼いだお金はどのように使っていますでしょうか?
稼いだお金は自分への投資に使うといいです。
自己投資の中身は以下にしましょう。
- ①知識
- ②スキル
- ③経験
- ④人間関係
- ⑤時間
知識とかスキルに関して、投資をして自分を磨いていく努力を続けた時、自分に向いていないのかもしれないと思う時があります。
その時、諦めるべきなのでしょうか。
本書ではその諦める基準は2年と書いてありました。
学問でも仕事でも、2年間集中的に努力すると素人とは違うレベルの領域にたどり着きます。
その時、有望なら時間と努力の投資を続ければいいですし、2年やってダメなら、たぶんその分野は自分に向いていないです。
人間関係は重要な資産なので、しっかり付き合っていくかを考えると良いです。
一般に、自分を変える方法は
- 付き合う人間を変える
- 時間の使い方を変える
の2通りだと言われているからです。
付き合っておくべきタイプの人は以下の3タイプです。
- 「頭のいい奴」
- 「面白い奴」
- センスが良くてチャンスを引っ張ってくるような人
- 「本当にいい奴」
- 真に心を許せるような人
そして、そのような人と付き合るためには自分もこの3種類のどれかのタイプにならないといけません。
転職について
転職しやすい昨今ですが、気に食わなかったらすぐに転職を繰り返すのは体力が要ります。
本書では転職していい理由を以下の3つと書いてありました。
- 仕事を覚えるための転職
- 仕事の能力を活かすための転職
- ライフスタイルを変えるための転職
転職には「コスト」がかかります。
そのコストとして意識しておくものとしては
- 転職の際に無収入になる期間の生活コスト
- キャリアの空白がもたらす人材価値の低下
- 転職での収入低下や年金・退職金の損失
など。
できることなら、間をあまりあけないで次の職に移れるようにすることが大切です。
最後に
これから前を向くために大切なことがたくさん書いてある本でした。