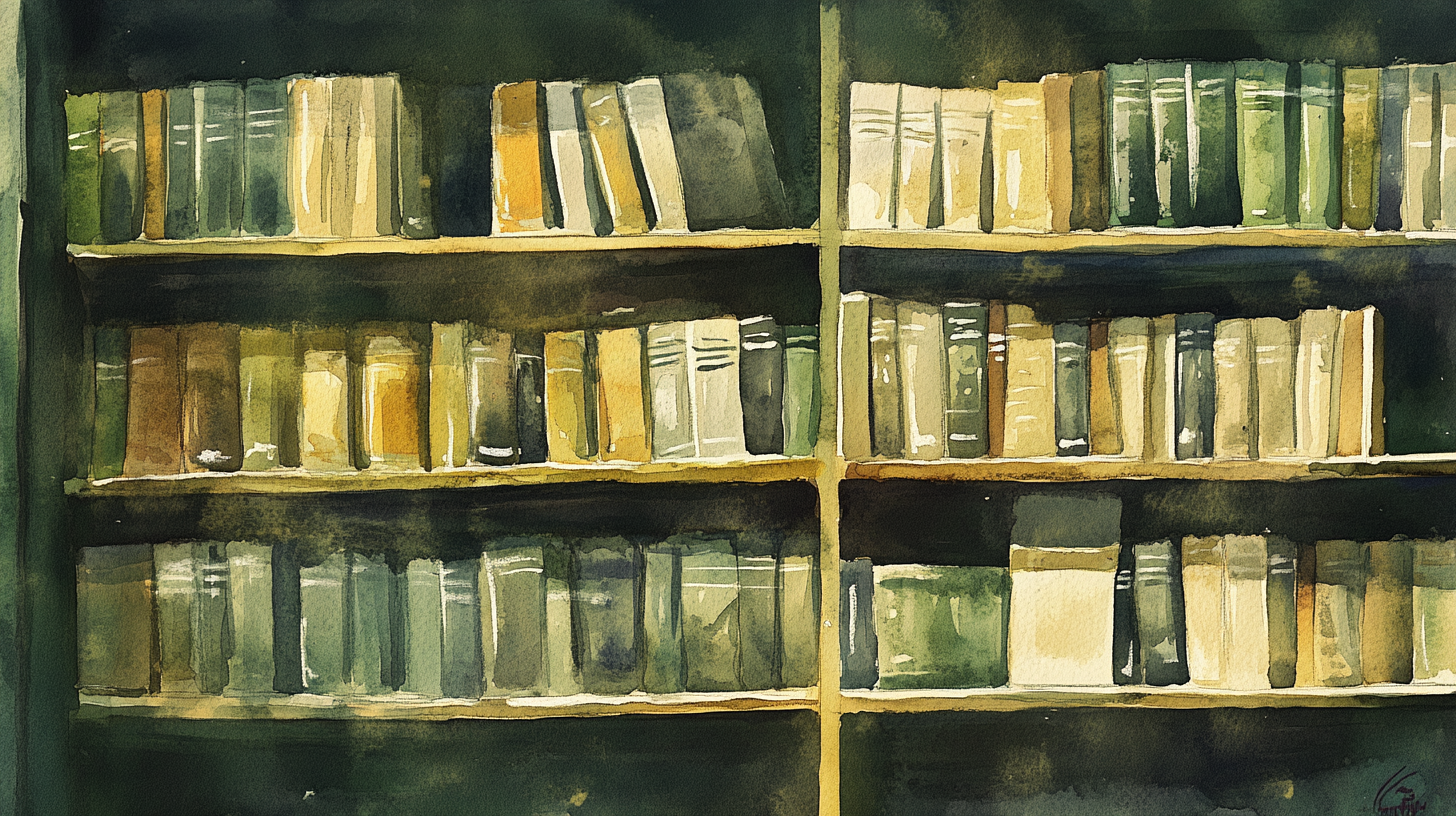はじめに
幸せを資本論として述べている本を見つけて読んでみました。
その名も『幸福の「資本」論――あなたの未来を決める「3つの資本」と「8つの人生パターン」』。
誰しもが幸せになりたい訳ですが、その幸せを資産として自分が持ち合わせるという考え方はとても興味深いです。
資本論で幸せを考えた時の最適解についてここに記そうと思います。
幸せを資本として考える
この本では幸せになるための要素として3つの資本を柱として考えています。
- 金融資産
- 人的資本
- 社会資本
の3つです。
✅金融資産
金融資産は分かりやすいです。お金です。
お金があれば、幸せにはある程度はなれると思います。
ある程度はね。
でも、お金がすべてではないことはみんな知っています。
お金だけが大量に会っても幸せにはなれません。
✅人的資本
人的資本は、健康や若さ、後はやりがいや個性ですね。
本書では、
人的資本とは自らの労働力を労働市場に「投資」して給与や報酬という「富」を得ること
と記載されています。
ようは、自分自身のことを表すものです。
✅社会資本
社会資本とはようは人脈です。
友達や信頼できる人が多い人の方が幸せになれます。
本書では、
まわりのひとたちとの関係性から「富」を得ること
と記載されていました。
ようは、人間関係、人脈のような人との絆に結び付くものです。
ちなみに、本書ではこれら3つを最大限に高めることは不可能と言っています。
どれか一つはある程度のあきらめが必要という事です。
で、以下の8つのパターンに分かれます。
- プア充
- 金融資産が低いし、まだ仕事に恵まれていないが、友達たくさんの人。若者に多い(社会資本だけが高い)
- リア充
- 高収入の職業に付ける人的資本を持ちつつ、友達や恋人のいる人(社会資本と人的資本が高い)
- お金持ち
- 信頼できる人が周りに少ないが、恵まれた仕事と十分な財産がある人(金融資産と人的資本が高い)
- 旦那
- 恵まれた仕事ではないが、金融資産はあって、人脈はある人(金融資産と社会資本が高い)
- 退職者
- 金融資産だけ残った人。高齢者に多い(金融資産が多い)
- ソロ充
- 結婚などに興味を持たず、稼いだお金は自分のために使う人(社会資本だけが高い)
- 貧困
- 3つの資本を全て持たない人(最貧困)
- 超充
- 3つの資本を全て持つ人。本書では実現不可と記載されていた
各資本はどのように上げていけばよいのか
3つの資本のそれぞれをどうやって高めていけばいいのでしょうか?
それぞれ見ていきます。
✅金融資産
お金の資産を増やす方法は色々ありますね。
日本はゆたかで安全な国なので恵まれている方です。
このため、特別な才能が無くても、勤勉と倹約により経済的にはある程度の安定が保証されます。
さらに、共働きをすればよりお金はたまっていく事でしょう。
また、アメリカでは年収7万5,000ドル、日本では年収800万円を超えると幸福度がほとんど上昇しないことが分かっているそうです。
となると、ある程度の年収さえあれば幸せは手に入る訳です。
逆に、年収800万を目指すことが稼ぎで幸せになるためのゴールになりますね。(800万って結構ありますけど😅)
さらに、資産で見ると、アンケート調査で金融資産が1億円を超えると幸福度が上がらないことが示されています。(アンケート調査ですけど)
また、お金持ちでも幸せでない人はいますが、これはお金のことを考えすぎて不幸になっているパターンです。(お金と不安の関係性についてはこちらの記事でも書いています。)
以上より、お金と幸福に関する法則は以下となります。
- 年収800万円(世帯年収1,500万円)までは収入が増えるほど幸福度は増す
- 金融資産1億までは、資産額が増えるほど幸福度は増す
- 収入と資産が一定額を超えると幸福度は変わらなくなる
✅人的資本
人的資本は富の資源です。
働ける自分を作ることで、富を生み出すことができます。
さらに、この資本は基本的に損失することがありません。
自己投資から失敗したとしても学ぶことが多いわけです。
そして、身に着けたスキルを活用できる場は日本という豊かな先進国であれば、多く存在します。
この人的資本を活用するかしないかで経済格差が広がることになります。
人的資本の投資の法則は以下になります。
- 収入は多ければ多いほどいい
- 同じ収入なら安定していた方がいい
- 同じ収入なら(あるいは収入が少なくても)自己実現できる仕事がいい
この3つめが人的資本を人的資本たらしめるポイントになります。
つまり、1と2だけならただ単に利益率の高いビジネスを選べばいいわけです。
3つめの自己実現は、心理学者のマズローの言う欲求の中でも高次の欲求です。
これは人が社会的な生き物だからこそ、社会や共同体の中でのかけがえのない自分になることを望みます。
かけがえのない自分になり自己実現をしながら、収益を最大化する戦略としては以下になります。
- 好きなことに人的資本のすべてを投入する
- 好きなことをマネタイズ(ビジネス化)できるニッチを見つける
- 官僚化した組織との取引から収益を獲得する
1と2はいいですね。
3については、大手企業の動きとして、組織の取引コストが大きくなってから、ベンチャー企業への投資を行い、成果が出た時に買収を試みます。
組織が官僚化することで、定型化された業務以外のことができなくなってくることが原因です。
定型化された業務以外のことは、アウトソースして成長を維持しようとします。
ベンチャー企業は上場してから事業を大手企業に売却する戦略になります。
✅社会資本
個人的に考えると、社会資本は性格が良ければ、友達も作れますし、好きな専門性があればそれで人脈も作れます。
その両輪があってこそ上質はコミュニティに身を置けるのではないのでしょうか。
つまり、好きなものを突き詰めて、似た者同士で人脈を作り、相手を蹴落とさないこと。
これに尽きます。
だから、他の2つの資本に比べて比較的ハードルが低いように感じます。
本書では人間関係を空間で分け、「政治空間」と「貨幣空間」に大きく分けています。
「政治空間」は友情とか愛情のある空間(関係性)、「貨幣空間」はお金で繋がる空間(関係性)です。
「政治空間」ではある種の平等性が意識されているので、自分の持っている富が大きくなると人間関係に金銭が介在するようになり、友情が崩れていくシナリオができます。
つまり、「政治空間」と「貨幣空間」同様に保つことはできません。
「政治空間」である友情の関係性は最大でも20~30人です。さらに範囲を広げるとなると、150人が最大となります。
これが個人を認識できる限界です。
一方で、「貨幣空間」はいくらでも広がります。
しかし、人生における「貨幣空間」の価値は極めて小さく、愛情の空間が人生の80%を占めるとした場合、貨幣空間は1%の比重しかないようです。
だからこそ、愛情空間と貨幣空間をしっかり分けることが大事ですね。
幸せの資本の最適解
3つの資本について記載しましたが、上記でも記載の通りこの3つの資本は最大限に高めることは不可能です。
では資本の分配はどうしていけばいいのでしょうか。
その最適解として以下のようにまとめています。
- 金融資産
- 「経済的独立」を実現すること⇒金銭的な不安から解放され、自由な人生を手にできる
- そのために、金融資本は金融市場に分散投資する
- 人的資本
- 自分のキャラを天職とし、「本当の自分」としての自己実現をする
- そのために、好きなことに集中投資をする
- 社会資本
- 政治空間から貨幣空間に移り、人間関係を選択できるようにし、小さな愛情空間と大きな貨幣空間に分散をする
最後に
性格のいい人が幸せになれる世の中が来てほしいですね。
性格のいい人、是非幸せになってください!